-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
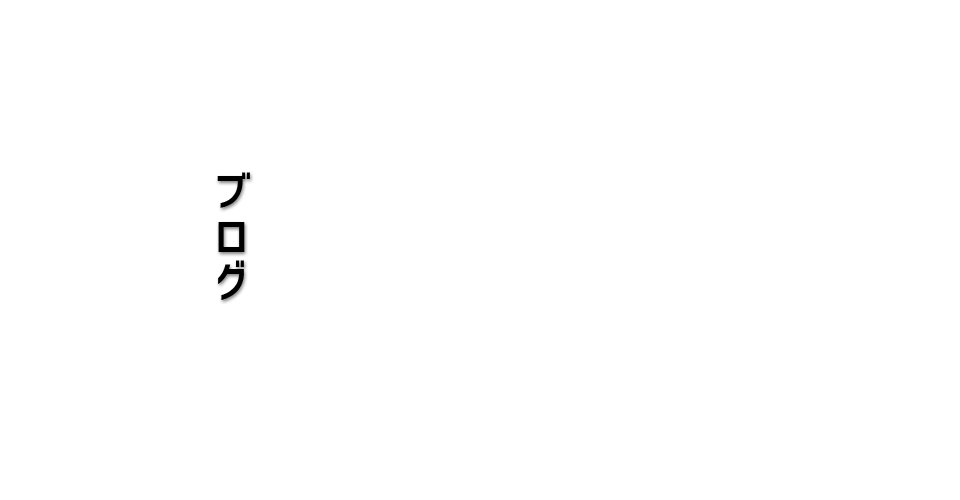
改修工事と聞くと、大掛かりなイメージがあるかと思いますが、その内容をあまり詳しくご存知ない方も多いのではないのでしょうか。
工期が長い改修工事だからこそ、その詳細を事前によく理解しておくことがとても大切です。
今回は、改修工事の意味や工事の特徴について、詳しくご紹介いたします。
[目次]
○改修工事の意味とは
○改修工事の特徴について
○まとめ
改修工事とは、建物に新しい設備を追加して、建物の性能をグレードアップさせる工事のことを指します。
たとえば、マンションにTVモニター付きのインターホンを導入したり、バリアフリー設備を目的に、段差を減らして手すり付きの設計にしたりなど、幅広い用途で工事がおこなわれます。
そのため、不動産価値の向上や、マンションなどにおいては入居率UPを目的に、改修工事を導入されることが多いのが特徴です。
改修工事を通して建物の状態を新しくし、不動産価値を上げることが、改修工事をおこなう意味とされています。
上述した内容を読まれると、「改修工事って、劣化箇所を修繕する工事じゃないの?」と疑問に思った方も多いかと思います。
というのも、改修工事は新しい設備を導入して建物の状態をグレードアップすることを目的としているため、建物の修繕がメインではありません。
改修工事と同様によく聞く、”大規模修繕工事”では、建物の修繕がメインであり、改修工事とは意味が異なります。
大規模修繕工事との違いについては、こちらの記事で詳しく説明していますので、ご参考にしてみてください。
改修工事の特徴としては、上述した通り、建物のグレードアップを目的として設備の導入を行うため、工期が長く大掛かりであり、修繕工事と比べて費用が高いことが挙げられます。
そのため目的によっては、工事の内容や費用も大きく変化するのが特徴です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は、改修工事の意味や工事の特徴について、ご紹介いたしました。
弊社では、工事に関するご相談から、現場の状態調査まで、無料で承っております。
気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[関連記事]
[ご相談受付]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
[NEXT]
屋上防水は施工からどれくらい持つのか、その耐用年数を気になっている方も多いかと思います。
施工後の効果の持続や剥がれにくさは、それぞれ防水材によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
今回は、屋上防水の耐用年数について、防水材ごとの特徴まで詳しく解説いたします。
[目次]
屋上防水で用いられる防水材は、主にウレタン防水、FRP防水、シート防水、アスファルト防水の4種類が多くみられます。
それぞれ特徴や仕上がり、工法が異なるため、屋上防水工事を施工するには、事前にそれらを確認しておくことが大切です。
以下にそれぞれの特徴と耐用年数を記載しますので、チェックしてみてください。
弊社では、ウレタン防水による屋上防水工事を推奨しております。
液体状の防水材になるため、さまざまな形状の屋上にも施工することが可能です。
耐用年数は10〜12年とされており、上からトップコートを重ね塗りすることで、強力な防水機能を発揮することができます。
ウレタン防水のように液体状の防水材が、このFRP防水です。
強力なプラスチック繊維が含まれているのを特徴とし、軽量であるため、木造の屋上への施工が適しているとされています。
塩化ビニールシートや、ゴムシートなどのシートを敷く防水です。
液状タイプのものと比べて、仕上がりの光沢が抑えられているのを特徴とします。
耐用年数はシートの素材によっても異なるため、事前に確認しておきましょう。
アスファルト防水とは、合成繊維不綿布にアスファルトを染み込ませ、その周りにコーティングしたシート状のルーフィングを用いた防水工法です。
アスファルト防水の中には、熱工法、トーチ工法、常温工法と3種類に分かれており、他の防水加工と比べて手間がかかる方法になります。
弊社では、屋上防水工事に置いて、ウレタン防水を多く使用しております。
ウレタン防水は、屋上の形状を問わず、幅広く施工が可能な防水材です。
液状の防水材を重ね塗りすることで、高い防水性を発揮し、屋上を丈夫な状態で長く保てるようになります。
また有害物質を含量がほかの防水材に比べて少ないため、人体への害がなく、環境にも配慮した防水材であるのが特徴です。
今回は、屋上防水のさまざまな種類についてご紹介いたしました。
なかでもウレタン防水は、工法も簡単でコストパフォーマンスに優れているため、弊社が推奨している防水材になります。
工法や費用についてこちらの記事でご紹介しておりますので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。
[ご相談受付]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
[NEXT]
エレベーターの底盤部であるエレベーターピットですが、そのメンテナンス方法をあまり詳しくご存知ない方も多いかと思います。
なかなか点検を行わないエレベーターピットだからこそ、その劣化のサインを見逃さないよう注意が必要です。
今回は、エレベーターピットの排水作業の必要性から、防水工事について詳しく解説いたします。
[目次]
エレベーターピットとは、エレベーターの最下部に位置する底盤部の箇所を指します。
建物の最下部のコンクリートを打設して造られるため、水が溜まりやすく、その排水が難しいのが特徴です。
エレベーターピットに水が溜まってしまうと、バクテリアなどの繁殖によりエレベーター内に異臭が生じたり、錆が広がることでエレベーター自体の老朽化に繋がります。
そのため、定期的な点検や排水作業、防水工事をおこなうことが必要です。
上述した通り、エレベーターピットには水が溜まりやすい特徴がありますが、そのまま放置してしまうと、ピット内だけでなくエレベーター自体の老朽化に繋がります。
そのような事態を防ぐためにも、定期的な点検と排水作業が必要です。
点検を行った際に水が溜まっていたり、水が蒸発した様な後が見つかる場合は、劣化が始まっているサインと言えます。
このような場合は、放置せず、すぐに排水作業をして、ピット内の状態を整えることが大切です。
エレベーターピット内に水が溜まっている場合は、水の通り道となっている部分の止水作業が必要です。
エレベーターピット防水工事では、漏水被害の原因となっている箇所をしっかり塞ぎ、防水加工を施して、ピット内の状態を丈夫に保ちます。
弊社では、エレベーターピット防水工事に置いて、薬液注入工法を用いて修繕するのが特徴です。
薬液注入による止水工法で遮水性を強化、そして防水材であるケイ酸質系防水材を施工することでより防水効果を発揮することができます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
劣化のサイン気づきにくい箇所であるからこそ、点検を行った際にはきちんと漏水していないか、劣化していないかを確認することがとても重要です。
弊社では、工事に関するご相談から現場の状態調査まで、無料で承っております。
気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[関連記事]
[保険申請や工事に関してのご相談]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
外壁塗装工事と言っても、あまりその内容を詳しくご存知ない方も多いかと思います。
古くなった外壁は、徐々に経年劣化のサインが見られるようになるため、状態がひどくなる前にも適切な工事を施すことが大切です。
今回は、外壁塗装工事の内容や、外壁が劣化した際に見られるサイン、そのほかの注意点について詳しくご紹介いたします。
[目次]
外壁塗装工事とは、古くなった建物の外壁の表面を綺麗に洗浄し、新しく外壁塗装を塗り替えて、外壁をリニュアールする工事のことを指します。
塗装を塗り替えるだけでなく、劣化して古くなった外壁の補修やひび割れなど修繕なども合わせておこなうのが特徴です。
塗布する外壁塗装の種類によって、仕上がりの特徴も異なるので、事前に工事後の外壁の仕上がりをイメージして塗料を選ぶことが大切です。
また用いる塗料ごとに、建物の外観と大きく変わります。
以下にそれぞれの外壁塗装の特徴を記載しますので、ご参考にしてみてください。
<シリコン塗料> 耐用年数:約10〜15年
外壁塗装において主流である塗料です。耐熱性や耐候性に優れており、汚れや色落ちに強い外壁に仕上げることができます。透湿性に富んでいるため、塗装膜が剥がれにくく、カビや藻が生じにくいという特長があります。
<ラジカル塗料> 耐用年数:約8〜16年
汚れに強く、変色がしにくいのを特徴とした塗料です。塗装したときの光沢を持ちを良く仕上げることができます。またチョーキング現象の発生を抑える効果も持ち合わせているのが、この塗料の特徴です。
<フッ素塗料> 耐用年数:約15〜20年
耐用年数が長く、高い耐久性を特徴としている塗料です。汚れがつきにくい性質があり、いつまでも外壁の外観を美しく保つことができます。親水性に富んでいるため汚れにくく、優れた防水性を持ち合わせています。
<セラミック塗料> 耐用年数:約10〜20年
砂や石、セラミックビーズなどの微粒子が配合された塗料で、無機塗料や無機ハイブリット塗料とも呼ばれています。遮熱・断熱効果を持ち合わせており、耐久性や耐候性に優れています。
<ウレタン塗料> 耐用年数:約8〜10年
価格が安く、密着性や耐久性、機能性のすべてにおいてコストパフォーマンスの良い塗料です。塗膜が柔らかく弾性があるので、伸縮性に優れており、ひび割れしにくい加工に仕上げることができます。
外壁塗装工事が必要されるタイミングとしては、前回の工事からおよそ10〜13年が経過した頃と言われていますが、マンションの立地や気候の影響によってそれらは左右されます。
特にこのチョーキング現象が起こっている場合は、紫外線や乾燥、雨風による経年劣化を受けて外壁が脆くなっている状態であり、修繕工事を必要とする状態と言えます。
チョーキング現象とは、建物の外壁を手でこすった時に白いチョークのような粉が付着する現象のことです。
外壁の表面樹脂の劣化を表すこの現象は、外壁の本来の防水性や耐紫外線などの機能を十分に発揮できていないことを表しています。
そのため、このチョーキング現象が起きている場合は、年数にかかわらず工事を施すことがおすすめです。
外壁塗装をおこなうにあたっては、主に2つの注意点が挙げられます。
一つ目の注意点は、工事の前に事前に住人の方や近隣の方のご理解をいただいておくことが必要になることです。
外壁塗装工事は、建物の周りに足場を設置しておこなう大掛かりな工事になります。
そのため、必ず事前に張り紙などでお知らせし、騒音や臭いが発生することへの了承を得ておくようにしてください。
二つ目の注意点としては、外壁の劣化箇所の修繕を念入りにおこなうことです。
どれだけ表面をきれいにしても、ひび割れなどの修繕がきちんとできていないと、外壁の防水性が弱くなり、劣化が進んでいってしまいます。
そのためひび割れ修繕の施工漏れが無いよう、工事前の劣化状態の調査を念入りにおこなうことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は、外壁塗装工事の内容や、外壁が劣化した際に見られるサイン、そのほかの注意点について詳しくご紹介いたしました。
弊社では、工事に関する業相談から、保険の申請、工事の施行まで、一貫して行っております。
気になることがございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
<NEXT>
火災保険はマンションの工事に適用できる?申請や注意点を解説!
[ご相談受付]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
コンクリートのひび割れ修繕において、バジリスクという言葉を耳にした方も多いかと思います。
バジリスクとは、その成分に含まれる自己治癒技術が注目を集めているひび割れ補修剤です。
今回は、このバジリスクの特徴や工法について、詳しくご紹介いたします。
[目次]
○バジリスクの特徴とは
○バジリスクの工法について
○まとめ
バジリスクとは、コンクリートに発生したひび割れを修繕する、液体補修剤のことを指します。
成分の中に含まれているバクテリアの代謝活動を利用することによって、コンクリートを自動的に治癒する効果があるのが特徴です。
コンクリート中に特殊なバクテリアと栄養分のカルシウム有機塩を混入することで、コンクリートにひび割れが発生した際にバクテリアの代謝活動によって損傷を自動的に修復するようになっています。
1回の塗布で0.2~0.3mmのひび割れ を、2-3回の塗布で最大0.6mmのひび割れを修復することができるため、コンクリートに発生したひび割れの修繕にぴったりです。
バジリスクを用いた修繕工事の工法としては、まずひび割れ内部を乾燥させ、補修剤が浸透しやすい状態を作るのが最初の段階です。
その後、A剤とB剤にわかれているバジリスクを、A剤から順に塗布していきます。
両方の補修剤を塗布し終わったら、あとはバジリスクの自己治癒技術に任せて放置させ、ひび割れの修復をはかります。
1日ほど経過したら、状態を確認し、問題なく修繕できているのを確かめたら、施工箇所を清掃して完了です。
このように、バジリスクの中に含まれているバクテリアの自己治癒技術を利用することで、簡単にひび割れの修繕ができるようになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今回は、バジリスクの特徴や工法についてご紹介いたしました。
弊社では、工事に関するご相談から現場の状態調査まで、無料でおこなっております。
なにか気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[NEXT]
[工事のご相談]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
屋上防水として人気のウレタン防水ですが、実際にどんな特徴やメリットがあるのか、あまりご存知ない方も多いかと思います。
ウレタン防水を用いて屋上の防水工事をおこなうには、事前にその詳細や、注意しておきたい点を理解しておくことが大切です。
今回は、ウレタン防水の注意点や耐久性、費用などについて詳しくご紹介いたします。
[目次]
ウレタン防水の耐久性は、施工からおよそ10〜12年ほどとされています。
液状の樹脂であるウレタン防水は、防水性に優れており、施行後の雨漏り被害や漏水被害を防ぐ効果があるのが特徴です。
また、ウレタン防水を重ね塗りしたり、上からトップコートを塗布することで、施工後の耐久性を強化することができます。
このトップコートの定期的な塗り替えが大切であり、この作業を施すことで、長い耐久性を保つことが可能です。
ウレタン防水の費用は、3,000〜5,000円/㎡が目安とされています。
屋上の広さや、形状、防水加工の厚さによって費用は変動しますので、あくまで目安としてご参考にしてください。
ウレタン防水の費用は比較的やすいのが特徴であり、ほかの屋上防水に比べてコストパフォーマンスに優れているのが特徴的です。
またトップコートの塗り替えは定期的に必要になりますが、塗り替えをおこなうことで、ウレタン防水自体の劣化を遅らせることができます。
そのため、長い目で見ると、結果的に費用が掛からずに済むのがメリットです。
ウレタン防水の施工にあたっては、主に注意点が3つあります。
一つ目は「下地処理をしっかりおこなうこと」、二つ目は「塗布する際のムラを無くすこと」、そして3つ目は「トップコートの塗り替えを必ずおこなうこと」です。
下地処理に関しては、ウレタン防水を塗布する前の作業になります。
ウレタン防水を塗布する前に、屋上の汚れや古い防水加工をきちんと撤去し、ひび割れなどの劣化箇所を修繕処理することがとても大切です。
また、ウレタン防水の施工時にムラができてしまうと、施工後の防水性にもばらつきが生まれてしまうため、均一に防水材を塗布する必要があります。
下地処理をしっかりおこなって、ムラなくウレタン防水を塗布した後は、必ずトップコートを塗布することが大切です。
屋上防水工事でウレタン防水を施工する際は、事前にこれらの注意点に配慮しながら工事を検討するようにしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今回は、ウレタン防水の注意点や耐久性、費用などについてご紹介いたしました。
弊社では、工事に関するご相談から現場の状態調査まで、無料でおこなっております。
なにか気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[NEXT]
[工事のご相談]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
地下コンクリートから水が出てきていたり、水溜りなどの漏水被害が見られる場合は、どうしたら良いかわからない方も多いかと思います。
地下コンクリートからの漏水は、被害が大きくなる前にも、早めの止水作業や工事を施すことが大切です。
今回は、地下コンクリートから漏水が見られる場合の対処法や、漏水工事について、詳しくご紹介いたします。
[目次]
地下コンクリートからの漏水は、建物の老朽化だけでなく、居住環境の衛生面にも大きく影響を及ぼします。
水漏れにより建物が湿っていると、カビやバクテリアが繁殖し、建物全体がカビ臭くなり、異臭被害の原因となってしまうのです。
そのため、少しでも水が蒸発したような跡があったり、水溜りができている場合は、危険信号のサインと言えます。
またそのような漏水被害を放置してしまうと、コンクリートが水の影響によって脆くなり、剥がれ落ちて中の鉄筋がむき出しになる”爆裂”という現象が起きるため注意が必要です。
被害が建物全体の耐久性にまで影響を及ぼす前にも、きちんと漏水被害への対処法をとるようにしましょう。
地下コンクリートの漏水工事では、ひび割れなどの劣化部分の修繕を施すことと、水の侵入を遮断することがポイントになります。
ひび割れ部分から既に水漏れが生じているのかどうかや、爆裂などの被害が起きていないかを調査し、様子を見ながら修繕していくことが重要です。
弊社の地下コンクリート漏水工事では、背面止水注入工法と呼ばれる工法を用いて、既存のコンクリートの漏水被害が見られる劣化箇所をしっかりと止水していきます。
その後工事箇所の状態に合わせて防水材を塗布し、内側からの止水性や防水性をつくるのが特徴です。
この工法で漏水工事をおこなうことによって、地下構造であるコンクリートの地盤強化が図れます。
また、周りの地盤を掘り起こす必要が無いため、地下まわりの地盤ごと行う工事に比べて工事費用が抑えられるのがポイントです。
地下コンクリートから漏水被害が見られる場合は、そのまま放置せずに、漏水工事を施すことが最善の対処法と言えます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は、地下コンクリートから漏水が見られる場合の対処法や、漏水工事について、詳しくご紹介いたしました。
弊社では、お電話による工事のご相談や、現場の調査まで無料で承っております。
何か気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[NEXT]
[ご相談受付]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
屋上防水が剥がれてくると、そろそろ防水加工を新しくしようとお考えの方も多いかと思います。
そんな屋上防水工事では、しっかりと剥がれの原因やさまざまな注意点を事前に理解しておくことが大切です。
今回は、屋上防水に剥がれが見られる際の原因と、工事の注意点や費用について、詳しくご紹介いたします。
[目次]
防水加工が施されている屋上は、年数が過ぎるとともに徐々に劣化が進んで剥がれが見られるようになります。
表面が剥がれる原因としては、この乾燥や雨などの天候による経年劣化が主な原因です。
劣化してくると、防水加工が剥がれて防水性が脆くなったり、下地がボロボロになって、ひび割れや小さな亀裂が発生するのが特徴です。
一度ひび割れが発生してしまうと、その部分に雨が降り注ぐことで、より経年劣化が進んで、錆びや腐食が始まるため注意が必要です。
屋上防水の剥がれを修繕するには、きちんとした手順で屋上防水工事を行う必要があります。
防水工事を施す際の注意点としては、きちんと既存の剥がれてしまった表面を綺麗に除去し、下地処理を施すことがポイントです。
下地処理によって防水材を施す際の土台をしっかり完成させることで、施行後の防水性と耐久性をきちんと保つことが可能になります。
また、施す防水加工の種類によっても、仕上がりや費用が異なるのも注意点として覚えておきましょう。
用いる防水材の種類や、屋上の広さ、防水加工の厚さによっても、費用は変動します。
弊社では、屋上防水工事において主にウレタン防水を用いておりますので、気になる方はこちらの記事をご確認ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は、屋上防水に剥がれが見られる際の原因と、工事の注意点や費用についてご紹介いたしました。
弊社では、お電話による工事のご相談や、現場の調査まで無料で承っております。
何か気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[NEXT]
[ご相談受付]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
上記の写真のように、駐車場にひび割れが発生しているのを発見したら、被害が大きくなる前にも、早めのうちから修繕を施すことが大切です。
とは言っても、実際に修繕には費用がいくらかかるのか、気になっている方も多いかと思います。
今回は、駐車場のひび割れ修繕について、その費用や工事の特徴を詳しくご紹介いたします。
[目次]
駐車場塗床工事では、はじめに状態の調査を行って劣化箇所を修繕した後、コテを使って塗床材を塗り、仕上げにコーティング材を塗布していきます。
コンクリートのひび割れ修繕工事においては、バジリスクという自己治癒型技術を持った修復剤を使用するのが、弊社が推奨している工法です。
バジリスクとは、バクテリアの代謝活動を利用した液状のひび割れ補修剤で、1回の塗布で0.2~0.3mmのひび割れ を、2-3回の塗布で最大0.6mmのひび割れを修復することができます。
バジリスク以外の修復法としては、主にエポキシ樹脂やアクリル樹脂を用いて修繕します。
構造クラックなどの大きいひび割れに対しては、エポキシ樹脂を用いて直接樹脂の注入を行い、強力な止水効果を発揮させます。
またアクリル樹脂は、水濡れしたひび割れ箇所にも対応できるため、エポキシ樹脂で補修できない漏水被害が見られるひび割れ箇所にぴったりの樹脂です。
駐車場のひび割れ修繕工事では、そのひび割れの大きさや、劣化状態、駐車場の広さによって金額が変更するのが特徴です。
古い塗膜や劣化した下地を全て削り取り、ひび割れや亀裂が見られる箇所に関しては、エポキシ樹脂やアクリル樹脂、バジリスク修復材を用いて修繕した後、塗床材を塗布します。
その塗床材の厚さによっても、費用が異なりますが、塗膜の厚さごとの目安としては、
1.0ミリ:4,400円/㎡
1.5ミリ:5,700円/㎡
2.0ミリ:7,000円/㎡
が費用の目安となります。(※MMA樹脂系塗床材の場合)
こちらの塗床材の費用に、ひび割れ修繕費用などが加わる形となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
弊社では、お電話による工事のご相談や、現場の調査まで無料で承っております。
何か気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[NEXT]
[ご相談受付]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉
エレベーターピットに水溜りができていたり、水漏れが起きている場合だと、どうしたら良いか分からなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。
点検をあまり行わないエレベーターピットだからこそ、漏水被害を発見したら、老朽化する前に工事を施すことが大切です。
今回は、エレベーターピットの水溜りはどうするべきかについて、排水作業や漏水工事に着目して解説いたします。
[目次]
エレベーターピットに水溜りができている場合は、錆びて劣化被害が生じる前にも、排水作業をおこなって、原因となっている箇所を修繕することが大切です。
排水作業としては、ピット内に溜まっていた水を建物の外へ排水し、その後に残った汚れを高圧洗浄機などで清掃します。
錆びや汚れを徹底的に取り除くことで、水溜りが生じる原因箇所を特定し、きちんと止水加工を施す準備が整うため、この作業はとても重要なポイントです。
エレベーターピットの漏水工事では、水溜りの排水作業や清掃、止水、防水材塗布の作業をおこなって、ピット内の漏水被害を修繕するのが一連の工事です。
止水作業においては、薬液注入工事を用いて、しっかりと原因箇所を止水するのが特徴です。
薬液注入工事とは、水の通り道となっている箇所に薬液を注入して、地盤を強化させる工法になります。
また薬液注入工事によって止水を施した後、ケイ酸質系防水材を塗布することで、ピット内の防水性を強化することが可能です。
コンクリートの毛細管空隙を充填し、その量を減少させコンクリートの表面を緻密なものに変化させることにより、防水性能を付与するものです。
排水作業と清掃によって漏水被害の原因を発見したエレベーターピットに、これらの止水・防水加工を施すことで、しっかりと漏水被害を遮断して防水性を維持させることが可能です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
弊社では、お電話による工事のご相談や、現場の調査まで無料で承っております。
何か気になる点がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。
[NEXT]
[ご相談受付]
[工事可能エリア]
東京都
(港区・中央区・豊島区・新宿区・世田谷区・渋谷区・大田区・千代田区・文京区・足立区・板橋区・練馬区・台東区・杉並区・葛飾区・北区・目黒区・江東区・墨田区・荒川区・中野区)
神奈川・埼玉・千葉